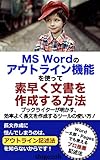AIIT(産業技術大学院大学)の第二学年PBL活動(研究室単位のプロジェクト活動)で役に立った文章の書き方を解説した電子書籍を紹介します。
所属するPBLによっては相当量のドキュメントを要求され、その内容もかなり厳しく指導されます。 2019年当時、論文その他ドキュメントの書き方がさっぱり分からなかったため、Amazon Kindle Storeで見つけた電子書籍を参考にしました。 紹介する電子書籍のほとんどはKindle Unlimitedで読むことができます(2019年10月時点)。
所属PBL
私が参加したPBL(研究室)の情報および参考書をもとに作成したドキュメントは以下です。
- 年度:2019年度
- 専攻:情報アーキテクチャ
- 科目:情報セキュリティ
- ドキュメント種類:学会発表(論文/スライド)、調査報告書
参考電子書籍(Kindle Unlimited)
「レポートの教科書」誰でも書ける論文・レポートの書き方簡単10ステップ
- 書名:「レポートの教科書」誰でも書ける論文・レポートの書き方簡単10ステップ
- サブタイトル:Anyone can write papers / reports Easy 10 steps
- 著者:嶋耕作
- 出版:ともしび出版
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07DHX48NL/
レポート/論文を書くための10ステップが書いてあるだけの本です。
各ステップで何をするかについては、メモ程度にしか説明していません。
この本を参考にレポート/論文を書くのは無理です。一回さっと目を通すだけで良いです。
裏口 日本語 校正入門 Vol.7
- 書名:裏口 日本語 校正入門 Vol.7
- サブタイトル:冬コミのカタログを勝手に校正してみた
- 著者:エンターメーカー
- 出版:記載なし
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07DSTJ6T7/
2016年冬コミのカタログを校正したというコンセプトの本です。
校正前の文と校正後の文そして変更の理由について簡単な説明が書かれています。
PBLで作成するドキュメントの校正にも使えるかと思い読んでみましたが、説明が簡単すぎて無理でした。
はじめての技術書ライティング
- 書名:はじめての技術書ライティング
- サブタイトル:IT系技術書を書く前に読む本
- 著者:向井 領治
- 出版:インプレスR&D
- URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B07BSC1T5T/
技術書を企画する手順から、構成の組み立、IT製品を本文中に記載するときの注意点まで詳しく説明しています。
説明されている内容は「技術書」に特化しており、論文のほか調査報告書など、PBLで要求されるドキュメント全般に適用できます。
「企画立案」から「校正」まで網羅しており、また電子書籍特有の事情まで踏み込んだ解説は必見です。
PBL期間中に電子書籍版と印刷物の両方を買ってしまいました。
読むと自分でもKindle本を書きたくなってきます。
本を書きたい人のための文章の基礎技術
- 書名:本を書きたい人のための文章の基礎技術
- サブタイトル:なし
- 著者:高橋 恵治
- 出版:武蔵野デジタル出版
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00UEYLK5G/
「書き言葉」と「話し言葉」の違い、「てにをは」の活用、「一文一義の原則」など基本的かつ重要なことを説明しています。
項目ごとに説明と具体例があり、非常に分かりやすいです。また、ページ数が少なく15分もあれば読み終われます。
ドキュメントを書き始める前に、一度目を通すことをお勧めします。
[新版]平成テクニカルライター養成講座
- 書名:[新版]平成テクニカルライター養成講座
- サブタイトル:なし
- 著者:武井一巳
- 出版:武井一巳 (Amazonの記載による)
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ANP2X3Y/
テクニカルライターになる方法を説明しています。
PC雑誌の記事やPCソフトのガイドブックなどのライターを想定しています。
企画書の作り方、企画の売り込み方、テクニカルライターとは何かについての説明など、とても興味深く読めました。
気分転換にはなります。
テクニカルライターが教える、文章の見た目を良くする技術
- 書名:テクニカルライターが教える、文章の見た目を良くする技術
- サブタイトル:なし
- 著者:晴海まどか
- 出版:白兎ワークス
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00G9W0PBC/
縦中横の使い方やアルファベットの取り扱いなど、見やすくて読みやすい文の書き方を説明しています。
基本的には縦書での説明ですが、横書きの場合についても補足があるためPBLドキュメントでも参照することができます。
特にカタカナ語とアルファベットの使い分けがについての説明が参考になりました。
入門テクニカルライティング
- 書名:入門テクニカルライティング
- サブタイトル:なし
- 著者:IT委員会
- 出版:マイハート社
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07J4RGSRB/
マニュアルその他技術文書を書く時の注意事項を説明しています。
用語の使い方から始まり、誤操作対策、初心者対策、数字、文字の使い方までが網羅されています。
PBLでは論文の他に説明スライドや作ったシステムの操作マニュアルを作成する場合がます。
この本もかなり役に立ちました。
MS Wordのアウトライン機能を使って素早く文書を作成する方法
- 書名:MS Wordのアウトライン機能を使って素早く文書を作成する方法
- サブタイトル:長文作成に怯んでしまうのは、「アウトライン記述法」を知らないからだ!
- 著者:しげぞう
- 出版:電筆文庫
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07TYMSMMV/
Microsoft Wordのアウトライン機能の使い方と、アウトライン機能を使ったドキュメント構成の考え方を説明しています。
操作画面の画像が載っており、Wordのどこをどのように操作すればいいのかが示されています。
この本で「アウトライナー」なる文章作成を効率化するソフトの存在を初めて知りました。
なお、PBL活動ではチームの方針(というか教員の指示)によりWordのアウトライン機能は使いませんでした。
参考電子書籍(買い切り)
理科系の作文技術(リフロー版)
- 書名:理科系の作文技術(リフロー版)
- サブタイトル:なし
- 著者:木下是雄
- 出版:中央公論新社
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01MDLGE9O/
PBLで技術文書を書くための参考書として指定されました。
Amazonでは印刷物の中古本が1円で買えますが、通勤時間に読むため電子書籍版も買いました。
これは・・・まあいいでしょう。
一回読んだら、もっと直接的に論文の書き方を学べる参考書に進みましょう。
Markdownライティング入門
- 書名:Markdownライティング入門
- サブタイトル:プレーンテキストで気楽に書こう!
- 著者:藤原 惟
- 出版:インプレスR&D
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07L5GDCMM/
PBLのメンバー(4人)で調査報告書を作成する必要があり、Markdownで書いたファイルをGit-Hubで管理できないかと思い読み始めました。
Markdownの素晴らしさとドキュメント生成ツールPandocの概要を理解できました。
結局、WORDファイルを手作業で連結させる方法にしたためMarkdownは使いませんでした。本としては面白かったです。
レポート・報告書 書き方と基本
- 書名:レポート・報告書 書き方と基本
- サブタイトル:なし
- 著者:HRS総合研究所
- 出版:すばる舎
- URL:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0091P79GS/
会社で作るレポート・報告書などの書き方を説明しています。
PBL活動で作成した議事録に教員から指摘が大量についたため、この本を導入しました。
会社で作る文書のみを対象としているため、PBL活動では出番がありませんでした。
備考
電子書籍を読む方法
今回紹介した書籍はすべてKindleで配信されています。そのため、ブラウザ/iPad mini/Androidタブレット/Kindleいずれでも読むことができます。
タブレット端末では、ページがカラーで表示され滑らかに動きます。検索のレスポンスも良好で快適な半面、ディスプレイが光るので長時間読むことはできません。
Kindleは、カラーは表示できずページ操作も遅めではありますが、画面が発光しないため目に負担がかからず楽に読むことができます。私はKindle Oasis(2019)で読みました。
本体が軽く通勤電車でも片手で扱えるのはとてもありがたいです。
まとめ
PBLでのドキュメント作成について、印刷物/参考サイト/電子書籍を読んで分かったことをまとめます。
- 書式や構成は論文にあわせる(教員の方針により微調整が必要)
- まずは文章の構成とサンプルのテキストを作成する
- 最後まで書ききってから内容を調整しないと時間が足りなくなる
- 誤字脱字のチェックには校正記号の書き込みが効果的
- 作成の手順は論文作成の参考書が役に立つ
- 構成の検討は技術書作成の参考書が役に立つ
- 参考書を読み込んだら、書いて修正してをとにかく繰り返してクオリティを上げるほかやりようがない
参考書には、一定以上書く練習しないと上達しない、とにかく書き続ける必要があると説明がありました。 実際その通りだと思います。 教員から論文指導を受けて「書いて繰り返して身に着ける」以外に対応の方法がないということがよくわかりました(実体験)。

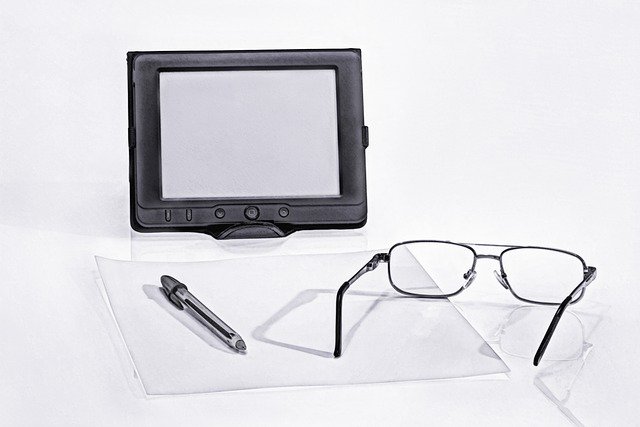




![[新版]平成テクニカルライター養成講座 [新版]平成テクニカルライター養成講座](https://m.media-amazon.com/images/I/51JOrUOA3fL._SL160_.jpg)